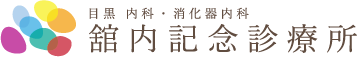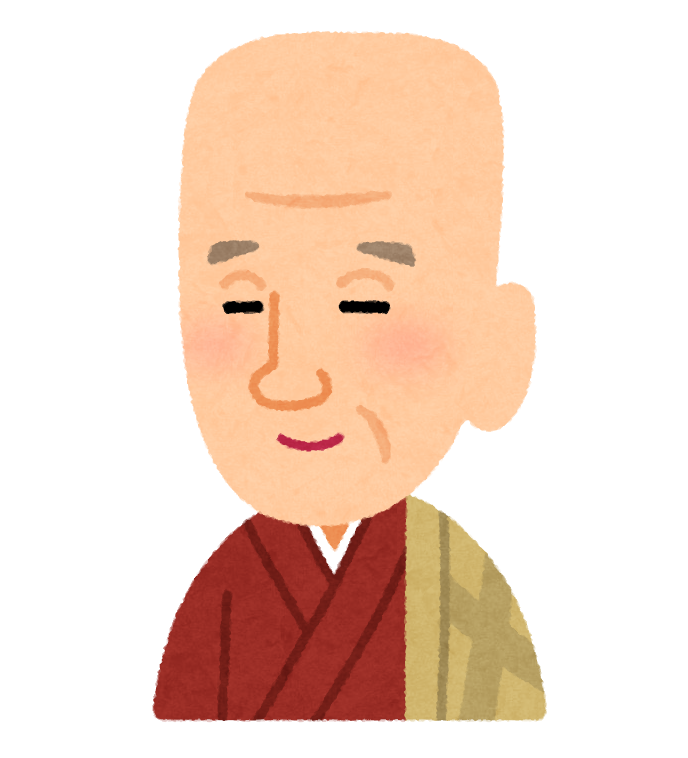「元の木阿弥」の謂れをご存知でしょうか。
木阿弥とは、人の名前だそうです。
天文19年(1550年)ごろ、戦国時代のお話です。
奈良、大和郡山の城主だった筒井順昭(つついじゅんしょう)は、息子の順慶(じゅんけい)がまだ幼かった時に病死しました。
幼かった息子を庇うため、逝去を隠すように遺言をしていました。
順昭の替え玉として、声が似ていた木阿弥という盲人の僧を招聘し、寝室に寝かせて訪問者を欺いていたそうです。
順慶が成人した後、順昭の逝去を公表しましたが、木阿弥は用済みとなってしまい、ニセ城主の生活から元の身分に戻ったというお話です。
これは、史実かどうか不明ですので、決して鵜呑みにしないようにお願いします。
ここでは、木阿弥が実在し、隠密に仕事を遂行したと仮に設定して、木阿弥の立場に近づいて、感じたことを述べています。
努力が実らず、振り出しへ戻る意味で良く使われている故事成句ですが、図らずも木阿弥は後世へ名を残すことになりました。
木阿弥は、どのような思いで城主に成り済ましたのでしょうか。
人に利用され、権力のもとで他人に成り済まし、刺客に怯え、一歩間違えれば敵はもとより味方から殺されるかも知れない。
厳重な健康管理と生活の制限を受け、家族とも合うことは禁じられていたに違いありません。
城主の遺言に従わなければ、更にまた違った意味で、身の危険に晒されることになるでしょう。
しかし、当時の状況から想像すると、命令に従わざるを得ません。
ただ単に、城主と声が似ていたというだけの理由で、木阿弥に白羽の矢が立ったことになります。
若し、何かの巡り合わせで依頼を受けたとしても、その役を演じるだけの才能と度胸がなければ、大役を成し遂げることは出来ません。
少なくとも、木阿弥は大役を演じ切った訳です。
良いか悪いかは別にして、自分の意思とは関係なく、図らずも有名になってしまいました。
意思に関わらず名を残す者、対して大多数の名もなき凡人との差は、一体どのようなものがあるのでしょうか。
もちろん、人から期待を受けるためには、何か魅力がなければなりません。
もしかすると自分の魅力は、気が付かないだけで、人から見れば価値があるものを、人それぞれ持っている可能性があります。
木阿弥の声が、眞にそれです。
自分には当たり前だと思えるものが、一部の人にだけ価値を持っていた訳です。
しかし、人から何かの価値を見出して貰ったとしても、更にもう一つの条件があります。
依頼を受け入れるだけの、懐が自分にあるか否かの違いです。
誰でも、危険から逃れようとします。
しかし、木阿弥の場合、逃れようとしても逃れない状態であったことは違いありません。
ここでは一般論になりますが、要は「リスクをどこまで背負うことが出来るか」という許容範囲を指しています。
言うまでもなく、リスクが無いものは見返りがなく、逆に大きな期待には、大抵の場合、大きなリスクが付き纏うものです。
そのようなリスクに対し、自分が許容する閾値を何処に置いているかの違いだと言えるでしょう。
自分の身に危険が及ぶような依頼を引き受ける人は、先ずいません。
若し居るとすれば、かなり危険に対して鈍感な人でしょう。
物事を成し遂げる人には、発想力や注意力、行動力、忍耐力などが必要です。
しかし、鈍感という資質は、努力しても決して得ることが出来ません。
そのような意味からすると、「天然の鈍感さ」という才能が、最も重要なのかも知れません。
役目を終えた木阿弥は、故郷で家族と共に安楽な余生を過ごしたと言われています。
戦国時代、城主の「影武者」を立てることは良くある話です。
この説話は嘘かも知れませんが、木阿弥を影武者として起用したという話は、何となく納得し易い理由になるかも知れません。
しかし、一般的に政治的な陰謀や策略に翻弄された人の末路は、闇に葬られて仕舞うものです。
役割を終えた木阿弥が、若し生きていなければ「元の木阿弥」という故事成句も無かったことになります。
元の生活に戻れたということは、仮にそれが史実であれば、手厚く抱えられに違いありません。
アベノミクスで築いた虚構の繁栄は、新コロナウイルス感染症という思わぬ伏兵で、見事に崩れ落ちました。
「元の木阿弥」レベルではなく、これから世界的な大恐慌へと更に転落して行くシナリオが容易に想像できます。
ウイルスという目に見えない敵は、別け隔てのない試練です。
この局面を、乗り切るために私達は何をすべきでしょうか。
盲目の木阿弥が与えられた役を果たしたように、私達は自身に与えられた役を今は唯、直向きに務めて行くのみであろうと思っています。
実際に木阿弥が居たかどうかは分かりませんが、木阿弥の存在を前提に、思いを馳せてみました。
舘内記念診療所